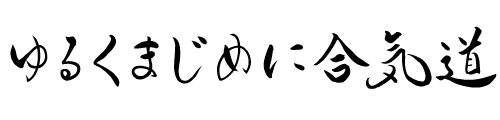こんにちは。
合気道三級のばーやんです。
「合気道は力が要らない」とよく言われますね。
でも、これは正確な表現ではありません。
正しくは「合気道では力を入れてはいけない」んです。
(まったく力が要らないわけでもないんですが、それはまた後述)
なぜ力を入れてはいけないんでしょうか?
答えは非常にシンプル。
力を入れてしまうと、技が効かないからです。
不思議ですよね。
普通は技を掛けるために身体を鍛えて力を付けるのに、合気道では力を抜けば抜くほど威力が増していきます。
その仕組みを僕なりの理解と解釈を加えつつご説明します。
あなたも一緒に考えてみてください。
力を入れると相手も力を入れる

こちらが力を入れると、相手もそれに反応するように力を入れ返してきます。
これは無意識というか反射的なものなので、相手が手練の武道家だろうが未経験の素人だろうが関係ありません。
誰でも同じように力を入れ返してきます。
そうなると技どころではありません。
ただ決まらないだけならまだしも、逆にやり返されてしまう恐れすらあります。
単なる力比べになってしまうので、結局は体格差による勝負になってしまうんですね。
なので、そうならないために合気道では「こっそり」動くことが重要です。
相手に気付かれないように、「いつの間にか崩されている」という状況を作るんです。
Wikipediaにはこんな記述があります。
無駄な力が入っていると、相手の反射的な抵抗を誘発し、接触点が外れる、力がぶつかって動きを止められる等の不具合が生じ、技の流れを阻害する。そのため「脱力」ということが特に推奨される。合気道 - Wikipedia
どうでしょうか。
ここに書かれている意味がわかりますか?
僕は未だにちゃんと分かってません(^^;
もしあなたもこの意味を理解できないのであれば、上級者に技を掛けてもらうことをおすすめします。
できれば、力を入れた場合と入れない場合の両方を掛けてもらって、比較できるようにしてください。
熟練者の技は、本当に「いつの間にか」としか表現しようがないほど、技が始まった瞬間にすら気付くことができません。
自ら体勢を崩しているかのような錯覚に陥るくらい、スムーズに導かれているんです。
僕はこの瞬間が楽しくて仕方ありません。
自分では考えてもいない動きを自分の身体がしている……。
不思議です。
でもこれが合気道の最大の魅力なんですよね。
あなたもぜひ自分の身体で体験してみてください。
力を入れると身体が硬くなる → イメージは自転車

ただ闇雲に「力を抜かないと」なんて考えていると、余計に力んで身体が硬くなってしまいます。
そんなときは、別の場面の感覚を思い出して当てはめてみましょう。
僕が最もイメージしやすいのは自転車です。
自転車のハンドルを握る手のように、余計な力を入れずリラックスした状態で、右だろうが左だろうがいつでも自由に曲がることができる。
かと言ってまったく力が入っていないわけではなく、まっすぐふらつかずに走れるようハンドルをコントロールするだけの力は入れている。
そんなイメージです。
乗り始めた頃はハンドルも力いっぱい握ってしまうし、ペダルもどうやって踏んだらいいか分かっていません。
身体の至る所が力んで、全身硬直していましたよね。
そうなると咄嗟に動くことが難しくなって、かえってバランスを崩したり転びやすくなったりします。
倒れそうになったときも、ちょっと足を伸ばせば普通に立てるのに、なぜか身体が固まってそのまま転んでしまった……。
なんてことは、多くの人が経験してるんじゃないでしょうか。
合気道も同じ。
力が入って身体が硬直してしまっては、正しく技を行うことができません。
逆に、正しく技を行うことができていれば、力を抜いた状態でも充分相手を制することができるんです。
相手を落とし穴に落とすために

もう一つのイメージとしては、「相手を落とし穴に落とす」というものがあります。
これは道場の大先輩からアドバイスをいただいた際に出てきた例えなのですが、その大先輩曰く、
落とし穴が見えないように草や土で隠すのが「力を入れない」という状態。
逆に、落とし穴が丸見えの状態が「力を入れている」状態。
落とし穴が見えている(=力が入っている)と、相手は落とし穴に落ちまい(=技に掛かるまい)とする。
とのことです。
言い得て妙ですね〜。
僕はこの説明を聞いて腑に落ちました。
(だからといってすぐにはできませんが……)
相手に気付かれないためにはどうしたら良いか。
いかに自然体のまま技に入れるか。
このあたりのことを考えながら稽古する必要がありそうですね。
合気道は技術の武道

合気道は技術がほぼすべてと言ってもいいくらい、最重要な要素です。
もちろん他の武道でも技術は重要ですが、それに加えてかなりの筋力が必要になります。
柔道や空手などを思い浮かべてもらえれば分かりやすいですね。
どんなに技術があっても、力が足りなければ投げることも蹴り倒すこともできません。
でも、合気道は違います。
正確に技が掛かりさえすれば、ほんの少しの力で確実に相手を制することができます。
合気道の技は人間の身体の構造に基づいて構成されています。
手首や肘、肩などの関節技が多いことからも分かりますね。
「このタイミングで、身体のここをこうすれば、必ず相手はこうなる」ということが、人体の構造上すでに決まっているんです。
稀に関節技がまったく効かない人も居ますけどね。
二教でどんなに極めても痛みを感じないとか。
まぁ、そんな人は例外中の例外です(笑)。
ほとんどの人は、正確に極まりさえすれば同じように痛みを感じますから。
もちろん痛みを感じなくとも動きを制することは可能です。
それもこれも技の正確さがあってこそ。
稽古の際にもこの「正確さ」を心掛けてください。
合気道は力が要らない?

合気道はまったく力が要らないかと言えば、そうでもありません。
相手の攻撃をさばいたり、相手の身体を制したりするわけですから、やはり最低限の力は必要になってきます。
(もちろん他の武道や格闘技と比べれば全然少ない力で事足りるのですが)
僕が道場で聞いて印象的だったのが、「力があるから抜くことができる。でも、なければ抜くこともできない」という言葉。
まさにその通りですね。
大きな力を出す余裕があるからこそ、力を抜くことができる。
つまり、「力を抜く(=入れない)」のと「力がない」のは違うんです。
例えるなら、軽自動車とスポーツカーの違いのようなもの。
同じ時速で走っていても、走行性能ギリギリで走っているのと、その気になれば 200km/h くらい軽く出せる能力を持ちながら走っているのでは、余裕の度合いが違います。
どちらが有利なのかは一目瞭然ですね。
5 の力が必要な技があったとします。
全力で 10 しか出せない人がその技を行おうとすると、50% の力を入れなければなりません。
それだけ力を入れてしまったら、相手が反応してしまう可能性もあります。
しかし、全力では 100 出せる人ならどうでしょうか。
たった 5% の力だけで技を行うことができます。
この程度であれば、恐らく相手は何も気付かず反応もしません。
力を入れないためにも、ある程度の力は備えておく必要があるということです。
まとめ
回りくどい説明になっているような気がしますが……。
言葉にするのは難しいですね。
僕もまだまだ勉強・研究中の身ですし。
ただ、合気道は「力を入れてはいけない」ということだけは確かです。
「力を抜く(入れない)」と「力がない」の違いについても、あなたなりに考えてみてくださいね。